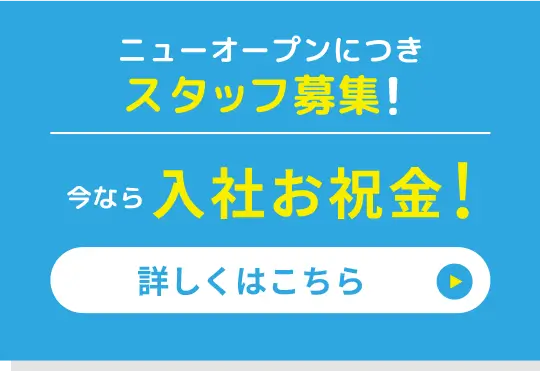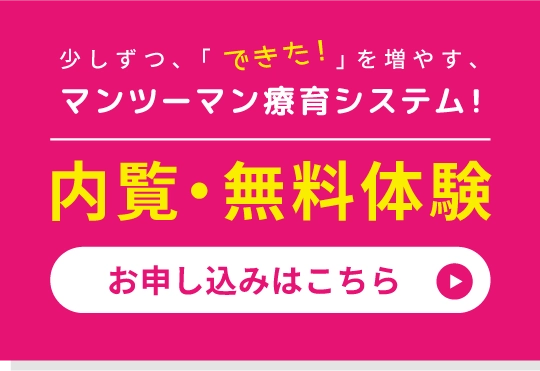支援プログラム
Support Program
「 事業所 」
ここから未来へ
児童発達支援
支援プログラムの作成日:令和6年8月1日
- 理念
-
- お子さまの「やりたい」「こうしたい」という気持ちを第一に、遊び(感覚統合)を通して「発達・成長」をサポートします。
- お子さまたち一人ひとりの「安心」「自信」「自立」に向けた支援を行います。
- 職員もお子さまたちと共に「成長」できる居場所を目指します。
- 支援方針
-
- お子さま一人ひとりの「できた!」を少しずつ増やしていき「自信」につながるよう支援いたします。
- それぞれのお子さまが異なる状況や背景を持っていることや、個々の欲求や個性を把握、理解し、お子さまが抱える課題や感情に寄り添い、共感することで「信頼関係」を築き「安心感」に繋げていきます。
- 「ありのままの自分でいられる場」を提供し、お子さまたちが自分に自信を持ち、ひとつでも多くの成功体験が重ねられるようにを目標にしています。
- 運動療育、感覚統合を通じ、お子さま一人ひとりの発達のステップアップに向けて「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間性・社会性」の5つの領域から総合的にアプローチし、支援します。
- 営業時間と
送迎 -
-
営業時間について
平日 11:00 ~ 19:00
休日 9:00 ~ 17:00
※夏休みなど長期休み期間中も同様です。 -
送迎について
行っておりません。保護者様での送迎をお願いしております。
-
- 本人支援
-
5領域と感覚統合
- 感覚統合はピラミッドのように発達し、しっかりと繋がることで「適応力」がつき、さまざまな能力が発揮できるようになります。
- 健康・生活
-
- 心と身体の健康の維持・増進
- 日々の療育の中で、心と身体の健康の維持・増進に努めています。 お子さまの健康状態の常なるチェックを行い基本的な生活スキルの向上を目指します。
- 好きな遊びを思い切り楽しめ、かつ、心地よく、安心して過ごせるために、環境や雰囲気づくりを心がけます。
- 運動・感覚①
-
- 自分が『次のステップ』に進むにはどんな刺激、運動が必要なのか、お子さま自身(脳や無意識の身体)が知っています。それがお子さまの「今、これがやりたい!」です。
- お子さまの「今、これがやりたい」を満足できるまで楽しんで活動していただき、感覚統合へと繋げていきます。
- 運動・感覚②
-
- 「固有受容覚」は、脳の目覚めや気持ちのコントロールなど、私たちが生活をスムーズに送る上で大切な役割を担っています。
- 生活の中で、手足にグッと力が入る感覚が感じることができるのは、固有受容覚が働いていてくれている証拠。
手足や身体が今どのように動いているのか、どれくらいのスピードやタイミングで身体を動かしたらいいのかというのを教えてくれています。 - 消しゴムを消すとき、どのくらいの力加減で消しゴムを動かせば紙がクシャクシャにならずに消したい文字だけ消すことができるかといったことに関わっているのが感覚です。
- 運動・感覚③
-
- 子どもたちは、大好きな人に抱きしめられることが大好きです。このぎゅーっと圧がかかるときにも固有受容覚というのは働いていて、「脳の目覚めの状態」や「気持ちのコントロール」にも関わってきます。
- このような「固有受容覚」以外の感覚、「残存している原始反射」にも遊びを通してアプローチし、お子さまの行動、遊びの意味、欲している感覚刺激を正しく理解しながら、お子さまの遊び(感覚統合)を共に楽しむことで発達を促していきます。
- 認知・行動
-
- お子さまは「安心できる場所」でご自分の本来の姿を出してくれます。 お子さまの「自己表現」「自己実現」が思う存分行えるよう信頼関係を築き「ここは自分の居場所なんだ」という安心感を大切にしております。
- ボディイメージの形成にもつなげます。運動あそびは身体感覚を養い、ボディイメージを形成します。
ボディイメージの形成は、物や人とぶつかることを減らし、力加減を調整することや、怪我のリスクを減らすことに繋がります。楽しい雰囲気の中で身体を動かし、さまざまな刺激を受け、状況に合わせた行動をコントロールするような成功体験を積み重ねていきます。
- 言語・コミュ
ニケーション -
- 遊びの中で言語だけでなく表情、仕草、身振り手振りなど、非言語的な要素も含めやり取りを「安心できる大人」と楽しみ、自分の思いを発信する経験をたくさん重ねられるようにいたします。
- 簡単な言葉でのやり取りなどを通して、人とのやり取りが楽しめるよう工夫したり、自分の思いを伝えられた達成感や、心地よさを味わえるように支援いたします。また、気持ちが受け止めてもらえた安心感も同時に味わえるように工夫をしていきます。
- 人間関係・
社会性 -
- 安心できる大人との関わり(やりとり)を楽しさの中で繰り返し、その中で、他者に関心が向いたり、抱けるよう、本児の興味の幅が広がっていくように工夫し支援していたします。
- 遊びの中でのやり取りなどを通して、コミュニケーションが楽しめるよう工夫したり、自分の思いを伝えられた達成感や、心地よさを味わえるようにする。また、気持ちが受け止めてもらえた安心感も味わえるように工夫をしていく。
- 家族支援
-
- ご家族様が安心して子育てをすることができるよう、困りごとに対する相談援助や、定期的なご家族様との面談の機会の設定を行います。
- お子さまの発達上のニーズについての気づきの促しとその後の支援を行います。
- お子さまの発達状況や特性の理解に向けた相談援助や必要に応じて各関係機関と連携しより良い支援ができるようにする。
- 移行支援
-
- ご家族様や移行先の事業所からのご希望があれば、支援方針、支援内容の共有や、お子さまのご様子についての伝達を行える準備を整えております。
- お子さまの進路や移行先の選択についてのご家族様への相談援助
- 保育所等と併行利用している場合では、併行利用先とのお子さまの状態や支援内容の共有ができるような体制を整えております。
- 併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整やお子さまのご様子についての共有を行える準備を整えております。
- 地域支援・
地域連携 -
- お子さまが通う保育所・学校等との情報連携や調整、支援方法や環境調整等に関する相談援助、放課後等デイサービス計画(児童発達支援計画)の作成又は見直しに関する会議の開催
- お子さまに支援を行う発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター、地域生活支援拠点等との連携
- お子さまが利用する障害児相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の障害児通所支援事業所との生活支援や発達支援における連携
- 虐待が疑われる場合には、児童相談所やこども家庭センターとの情報連携
- 個別のケース検討のための会議への参加
- 職員の
質の向上 -
【支援に関わる人材の知識・技術を高めるため以下の取り組みを行います】
- 入職時には療育・運動等についての研修への参加とレポートの作成
- 自治体や児童発達支援センター、障害児支援関係団体が実施する研修等への参加
- 事業所における研修会や勉強会の開催
- 職員を他の事業所等に派遣しての研修
- 事業所内における職員の自己研鑽のための図書の整備等
- 強度行動障害支援者養成研修や中核的人材養成研修の受講
- 主な行事等
-
- 予告のないスケジュールや環境設定の変更、サプライズ等の見通しのつかない(予期しない)出来事を得意としないお子さまも、中にはいらっしゃいますので、季節のイベントごとなどは、現在行っておりません。
- ですが、お子さま、ご家族様からのご要望があれば、可能な限り季節感を味わえるような活動の提供を工夫して行っていきたいと思います。
放課後等デイサービス
支援プログラムの作成日:令和6年8月1日
- 理念
-
- お子さまの「やりたい」「こうしたい」という気持ちを第一に、遊び(感覚統合)を通して「発達・成長」をサポートします。
- お子さまたち一人ひとりの「安心」「自信」「自立」に向けた支援を行います。
- 職員もお子さまたちと共に「成長」できる居場所を目指します。
- 支援方針
-
- お子さま一人ひとりの「できた!」を少しずつ増やしていき「自信」につながるよう支援いたします。
- それぞれのお子さまが異なる状況や背景を持っていることや、個々の欲求や個性を把握、理解し、お子さまが抱える課題や感情に寄り添い、共感することで「信頼関係」を築き「安心感」に繋げていきます。
- 「ありのままの自分でいられる場」を提供し、お子さまたちが自分に自信を持ち、ひとつでも多くの成功体験が重ねられるようにを目標にしています。
- 運動療育、感覚統合を通じ、お子さま一人ひとりの発達のステップアップに向けて「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間性・社会性」の5つの領域から総合的にアプローチし、支援します。
- 営業時間と
送迎 -
-
営業時間について
平日 11:00 ~ 19:00
休日 9:00 ~ 17:00
※夏休みなど長期休み期間中も同様です。 -
送迎について
行っておりません。保護者様での送迎をお願いしております。
-
- 本人支援
-
5領域と感覚統合
- 感覚統合はピラミッドのように発達し、しっかりと繋がることで「適応力」がつき、さまざまな能力が発揮できるようになります。
- 健康・生活
-
- 心と身体の健康の維持・増進
- 日々の療育の中で、心と身体の健康の維持・増進に努めています。 お子さまの健康状態の常なるチェックを行い基本的な生活スキルの向上を目指します。
- 好きな遊びを思い切り楽しめ、かつ、心地よく、安心して過ごせるために、環境や雰囲気づくりを心がけます。
- 運動・感覚①
-
- 自分が『次のステップ』に進むにはどんな刺激、運動が必要なのか、お子さま自身(脳や無意識の身体)が知っています。それがお子さまの「今、これがやりたい!」です。
- お子さまの「今、これがやりたい」を満足できるまで楽しんで活動していただき、感覚統合へと繋げていきます。
- 運動・感覚②
-
- 「固有受容覚」は、脳の目覚めや気持ちのコントロールなど、私たちが生活をスムーズに送る上で大切な役割を担っています。
- 生活の中で、手足にグッと力が入る感覚が感じることができるのは、固有受容覚が働いていてくれている証拠。
手足や身体が今どのように動いているのか、どれくらいのスピードやタイミングで身体を動かしたらいいのかというのを教えてくれています。 - 消しゴムを消すとき、どのくらいの力加減で消しゴムを動かせば紙がクシャクシャにならずに消したい文字だけ消すことができるかといったことに関わっているのが感覚です。
- 運動・感覚③
-
- 子どもたちは、大好きな人に抱きしめられることが大好きです。このぎゅーっと圧がかかるときにも固有受容覚というのは働いていて、「脳の目覚めの状態」や「気持ちのコントロール」にも関わってきます。
- このような「固有受容覚」以外の感覚、「残存している原始反射」にも遊びを通してアプローチし、お子さまの行動、遊びの意味、欲している感覚刺激を正しく理解しながら、お子さまの遊び(感覚統合)を共に楽しむことで発達を促していきます。
- 認知・行動
-
- お子さまは「安心できる場所」でご自分の本来の姿を出してくれます。 お子さまの「自己表現」「自己実現」が思う存分行えるよう信頼関係を築き「ここは自分の居場所なんだ」という安心感を大切にしております。
- ボディイメージの形成にもつなげます。運動あそびは身体感覚を養い、ボディイメージを形成します。
ボディイメージの形成は、物や人とぶつかることを減らし、力加減を調整することや、怪我のリスクを減らすことに繋がります。楽しい雰囲気の中で身体を動かし、さまざまな刺激を受け、状況に合わせた行動をコントロールするような成功体験を積み重ねていきます。
- 言語・コミュ
ニケーション -
- 遊びの中で言語だけでなく表情、仕草、身振り手振りなど、非言語的な要素も含めやり取りを「安心できる大人」と楽しみ、自分の思いを発信する経験をたくさん重ねられるようにいたします。
- 簡単な言葉でのやり取りなどを通して、人とのやり取りが楽しめるよう工夫したり、自分の思いを伝えられた達成感や、心地よさを味わえるように支援いたします。また、気持ちが受け止めてもらえた安心感も同時に味わえるように工夫をしていきます。
- 人間関係・
社会性 -
- 安心できる大人との関わり(やりとり)を楽しさの中で繰り返し、その中で、他者に関心が向いたり、抱けるよう、本児の興味の幅が広がっていくように工夫し支援していたします。
- 遊びの中でのやり取りなどを通して、コミュニケーションが楽しめるよう工夫したり、自分の思いを伝えられた達成感や、心地よさを味わえるようにする。また、気持ちが受け止めてもらえた安心感も味わえるように工夫をしていく。
- 家族支援
-
- ご家族様が安心して子育てをすることができるよう、困りごとに対する相談援助や、定期的なご家族様との面談の機会の設定を行います。
- お子さまの発達上のニーズについての気づきの促しとその後の支援を行います。
- お子さまの発達状況や特性の理解に向けた相談援助や必要に応じて各関係機関と連携しより良い支援ができるようにする。
- 移行支援
-
- ご家族様や移行先の事業所からのご希望があれば、支援方針、支援内容の共有や、お子さまのご様子についての伝達を行える準備を整えております。
- お子さまの進路や移行先の選択についてのご家族様への相談援助
- 保育所等と併行利用している場合では、併行利用先とのお子さまの状態や支援内容の共有ができるような体制を整えております。
- 併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整やお子さまのご様子についての共有を行える準備を整えております。
- 地域支援・
地域連携 -
- お子さまが通う保育所・学校等との情報連携や調整、支援方法や環境調整等に関する相談援助、放課後等デイサービス計画(児童発達支援計画)の作成又は見直しに関する会議の開催
- お子さまに支援を行う発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター、地域生活支援拠点等との連携
- お子さまが利用する障害児相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の障害児通所支援事業所との生活支援や発達支援における連携
- 虐待が疑われる場合には、児童相談所やこども家庭センターとの情報連携
- 個別のケース検討のための会議への参加
- 職員の
質の向上 -
【支援に関わる人材の知識・技術を高めるため以下の取り組みを行います】
- 入職時には療育・運動等についての研修への参加とレポートの作成
- 自治体や児童発達支援センター、障害児支援関係団体が実施する研修等への参加
- 事業所における研修会や勉強会の開催
- 職員を他の事業所等に派遣しての研修
- 事業所内における職員の自己研鑽のための図書の整備等
- 強度行動障害支援者養成研修や中核的人材養成研修の受講
- 主な行事等
-
- 予告のないスケジュールや環境設定の変更、サプライズ等の見通しのつかない(予期しない)出来事を得意としないお子さまも、中にはいらっしゃいますので、季節のイベントごとなどは、現在行っておりません。
- ですが、お子さま、ご家族様からのご要望があれば、可能な限り季節感を味わえるような活動の提供を工夫して行っていきたいと思います。